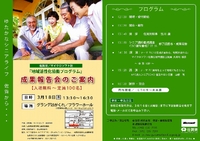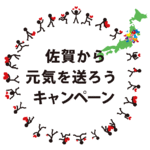2008年01月14日
u-さが「もやい」ネットワーク
「もやい」とは佐賀の方言で「共有」を意味する言葉です。同時に人と人との「つながり」をも意味します。
佐賀県では「もやい」をキーワードにして、2010年代の佐賀の地域活性化をICTを活用して行おうと構想しています。
昔ながらの村共同体的な温かい人と人との繋がりを、ICTを道具として使い補完しようと考えています。
「u-さが」はキャッチフレーズです。
この構想について、私の個人的な意見を述べさせてもらいます。

≪u-リテラシー、u-コミュニティについて≫
ネットを使ったコミュニティを実現するには、情報リテラシーの向上が必須。
そのためにはICTの有用性を理解してもらわなければならない。
しかし、ICTに懐疑的な人に頭ごなしに言っても、逆に反発されるだけ。
同じ目線でその人に合った有用性を実演して見せる事が必要。
何がその人に合った有用性か?
そもそもインターネットが現在のように普及したのは、それが人間の欲望を満たす物だったからです。
つまり「風俗系」のサイトが普及を促進しました。また、「オタク文化」も日本人の感性にマッチしていたために、
ネット上に瞬く間に普及しました。
日本人は個人プレイは不得意ですが、匿名の不特定多数で発言します。
それでいながら他人と違う自分を主張したい、これがネットワーク上の「オタク文化」達なのです。
しかし、これはオタク達だけの特殊性ではありません。
日本人が本来持っている特性の端的な表れです。
現在はこれがネット利用の主要層の、若い世代の嗜好に偏っているだけです。
この偏りを広い世代・業種・地域に分散させる事が、ICT普及のカギだと思います。
つまり、色々な層の実生活に密着した『道具』としてのICTの有用性を見せる事が必要です。
例えばシニア層に趣味にICT応用をして見せたり、障害者に不自由な方に障害の度合いに合った使用法を教えてたりする。
また子育て中の若いママに、子育てベテランの女性がネットで指導する。
農業分野でも、高い技術を持った農家が現場で携帯動画等を使い指導をする等です。
このよう事は既に行っていたと言われるかもしれません。
しかし、それはパソコンスクールやパソコン講座で上から教えると言った物で、相手の目線に降りて共に考えるといった物ではありません。
地域の公民館、学校または個人の家でも構いません、少数のやる気の有る人に有用性を知ってもらうことが大切です。(ITキャラバン)
とにかく切欠を作ってやるのです。
その後、興味を持った人はパソコンスクールや講座で勉強すればよい。
それでスキルアップした人達が、今度は地域で啓蒙する立場になってもらうのです。(自分の持つ知識や技術が、必要とされている事の実感)
優秀な人は講師になってもらってよいでしょう。
別にICTの講師ではありません、趣味、子育て、農業等の講師です。
ただICTを『道具』として使って、より分かりやすく効率的に指導する講師です。
この方法は時間が掛かります。
しかし、今まで国や県や地方自治体も色々な方法でICTの普及を行ってきましたが、思うように普及しない現状を考えて下さい。
既存の方法では限界だと言う事です。
原点に戻って地道な啓蒙・普及活動をすべきです。
ある程度のリーダーが育てば、どこかの時点で普及が加速するのではないでしょうか。
≪学校教育の分野について≫
小学生が使う場合システムで閲覧制限を掛ける事は勿論必要です。
ですが子供は大人が考える以上にIT機器を使いこなし、マニュアルに無い使い方を思い付きます。システムだけでは保護しきれません。
例えは悪ですが、性教育と同じです。隠しても何所かで知ってしまうのです。
学校ではITを成績を上げるためだけに使おうとしているようですが、それでけでは子供はITを変な使い方しかしません。
小学生低学年からITを使う上のマナーやモラルを教えるべきです。
小学生高学年になったら、ネット上の犯罪などから自分を守るためセキュリティー概念を教えるべきではないでしょうか。
≪高齢化・少子化の分野について≫
独居老人向けの話相手的なコールセンターの設置。
簡単な入力デバイスの開発必要。
≪地域コミュニティの分野について≫
地域コミュニティにGISを取り入れれば、視覚的に分かり易い。
高齢者の知る伝承や、地域の風俗の映像記録を残す。
高齢者に自分の持つ情報に価値が有る事を知ってもらう。
≪ICTを活用した地域産業の分野について≫
農業分野での応用については、安全・安心とトレーサビリティが重要なキーワードだと言う事は話しました。
農薬や肥料に情報をバーコードやQRコードを携帯や専用リーダーで読み取り、データベースサーバーで一括管理する。
農園・畜舎をライブカメラで撮影して動画配信する。
前記の情報と、気象や市況などの情報を総合的に分析し、農家に技術指導する。
指導は農協や農業改良普及所などが、総合的は情報管理センターを設置して官民共同で管理する。
これらITCで管理した産物の付加価値として市場に投入する。
販売チャンネルを増やすために、農地トラストや消費者への直売を考える。
また、農産物が過剰生産された場合には、安く地域に販売するシフトする。
生産者と消費者の交流が深まれば、グリーン・ツーリズム等を実施しする事で、リアルな交流からより強い流通のパイプを形成出来る。
これらの事は個々には既に実施例が有るかも知れません。
しかし、県単位の様は広域での総合的な実施例は無い。
第1産業が主流の佐賀県では、農林漁業にICTを活用し収益を上げる
事が他産業の活性化にも繋がると思う。
また、海外への販売にも有効な手段となるだろう。
≪ポイントシステム(地域通貨)について≫
情報リテラシーの啓蒙・普及の観点で、お互いの情報を相手に提供や指導をして、全てが先生であり同時に生徒と関係を作っていく。
そのサービスの交換代価を、ポイントシステムで管理してはどうだろうか。
“構想に対する懸念”
この構想の「お題目」は素晴らしいものですが、実行に当たっての具体的な内容がハッキリしない。
それにこの構想を実現するには、末端の県民の情報リテラシーが徹底的に不足している。
大きな構想は示すことは確かに必要なことだが、同時に足元をしっかり固めることも大事である。
両方が巧くバランスしなければ実現は無理だろう。
しかし、現在の佐賀県の状況は必ずしも好ましく無い。
県のトップは構想の実現に向けて意欲を見せてはいるが、行政の幹部がそれに付いて来ていない。役所の悪い癖で変化嫌うのだ。
でも誰が見ても現況で佐賀県が長期に渡って活性化する兆しは見えない。宮崎県知事ではないが、「どがんかせんといかん」状況だ。
これではトップには耳に気持ち良い事がばかりが伝わり、実際の現場は全然動いていない状況になるだろう。
歴史上どんなに優れた指導者でも、組織の情報の流れが滞り崩壊した例は枚挙にいとまがない。
情報化事業が、情報が原因で失敗していたのでは目も当てられない。
行政だけではない、小・中学校のICT分野の指導力不足ははっきりしている。
しかし、教師にそれを求めるのは無理なのも現状だ。
学校はもっと柔軟に外部の力を受け入れるべきだと思う。
社会教育を担う大学にも問題はある。お余りにも指導方法が一般人には馴染まないのだ。
もっと現場の目線での指導方法を研究してほしい。
民間企業にも問題がある。
特にこの事業の先頭に立つべきIT関連企業が、短期的な利益だけに目がいっている気がする。
そのために、事業そのものに反対に企業すら見受けられる。
もっと中・長期的視野での視点で事業に取り組んでほしい。
それが結果的には自社の利益につながるのだから。またそうしなければ生き残っていけない。
佐賀県では「もやい」をキーワードにして、2010年代の佐賀の地域活性化をICTを活用して行おうと構想しています。
昔ながらの村共同体的な温かい人と人との繋がりを、ICTを道具として使い補完しようと考えています。
「u-さが」はキャッチフレーズです。
この構想について、私の個人的な意見を述べさせてもらいます。

≪u-リテラシー、u-コミュニティについて≫
ネットを使ったコミュニティを実現するには、情報リテラシーの向上が必須。
そのためにはICTの有用性を理解してもらわなければならない。
しかし、ICTに懐疑的な人に頭ごなしに言っても、逆に反発されるだけ。
同じ目線でその人に合った有用性を実演して見せる事が必要。
何がその人に合った有用性か?
そもそもインターネットが現在のように普及したのは、それが人間の欲望を満たす物だったからです。
つまり「風俗系」のサイトが普及を促進しました。また、「オタク文化」も日本人の感性にマッチしていたために、
ネット上に瞬く間に普及しました。
日本人は個人プレイは不得意ですが、匿名の不特定多数で発言します。
それでいながら他人と違う自分を主張したい、これがネットワーク上の「オタク文化」達なのです。
しかし、これはオタク達だけの特殊性ではありません。
日本人が本来持っている特性の端的な表れです。
現在はこれがネット利用の主要層の、若い世代の嗜好に偏っているだけです。
この偏りを広い世代・業種・地域に分散させる事が、ICT普及のカギだと思います。
つまり、色々な層の実生活に密着した『道具』としてのICTの有用性を見せる事が必要です。
例えばシニア層に趣味にICT応用をして見せたり、障害者に不自由な方に障害の度合いに合った使用法を教えてたりする。
また子育て中の若いママに、子育てベテランの女性がネットで指導する。
農業分野でも、高い技術を持った農家が現場で携帯動画等を使い指導をする等です。
このよう事は既に行っていたと言われるかもしれません。
しかし、それはパソコンスクールやパソコン講座で上から教えると言った物で、相手の目線に降りて共に考えるといった物ではありません。
地域の公民館、学校または個人の家でも構いません、少数のやる気の有る人に有用性を知ってもらうことが大切です。(ITキャラバン)
とにかく切欠を作ってやるのです。
その後、興味を持った人はパソコンスクールや講座で勉強すればよい。
それでスキルアップした人達が、今度は地域で啓蒙する立場になってもらうのです。(自分の持つ知識や技術が、必要とされている事の実感)
優秀な人は講師になってもらってよいでしょう。
別にICTの講師ではありません、趣味、子育て、農業等の講師です。
ただICTを『道具』として使って、より分かりやすく効率的に指導する講師です。
この方法は時間が掛かります。
しかし、今まで国や県や地方自治体も色々な方法でICTの普及を行ってきましたが、思うように普及しない現状を考えて下さい。
既存の方法では限界だと言う事です。
原点に戻って地道な啓蒙・普及活動をすべきです。
ある程度のリーダーが育てば、どこかの時点で普及が加速するのではないでしょうか。
≪学校教育の分野について≫
小学生が使う場合システムで閲覧制限を掛ける事は勿論必要です。
ですが子供は大人が考える以上にIT機器を使いこなし、マニュアルに無い使い方を思い付きます。システムだけでは保護しきれません。
例えは悪ですが、性教育と同じです。隠しても何所かで知ってしまうのです。
学校ではITを成績を上げるためだけに使おうとしているようですが、それでけでは子供はITを変な使い方しかしません。
小学生低学年からITを使う上のマナーやモラルを教えるべきです。
小学生高学年になったら、ネット上の犯罪などから自分を守るためセキュリティー概念を教えるべきではないでしょうか。
≪高齢化・少子化の分野について≫
独居老人向けの話相手的なコールセンターの設置。
簡単な入力デバイスの開発必要。
≪地域コミュニティの分野について≫
地域コミュニティにGISを取り入れれば、視覚的に分かり易い。
高齢者の知る伝承や、地域の風俗の映像記録を残す。
高齢者に自分の持つ情報に価値が有る事を知ってもらう。
≪ICTを活用した地域産業の分野について≫
農業分野での応用については、安全・安心とトレーサビリティが重要なキーワードだと言う事は話しました。
農薬や肥料に情報をバーコードやQRコードを携帯や専用リーダーで読み取り、データベースサーバーで一括管理する。
農園・畜舎をライブカメラで撮影して動画配信する。
前記の情報と、気象や市況などの情報を総合的に分析し、農家に技術指導する。
指導は農協や農業改良普及所などが、総合的は情報管理センターを設置して官民共同で管理する。
これらITCで管理した産物の付加価値として市場に投入する。
販売チャンネルを増やすために、農地トラストや消費者への直売を考える。
また、農産物が過剰生産された場合には、安く地域に販売するシフトする。
生産者と消費者の交流が深まれば、グリーン・ツーリズム等を実施しする事で、リアルな交流からより強い流通のパイプを形成出来る。
これらの事は個々には既に実施例が有るかも知れません。
しかし、県単位の様は広域での総合的な実施例は無い。
第1産業が主流の佐賀県では、農林漁業にICTを活用し収益を上げる
事が他産業の活性化にも繋がると思う。
また、海外への販売にも有効な手段となるだろう。
≪ポイントシステム(地域通貨)について≫
情報リテラシーの啓蒙・普及の観点で、お互いの情報を相手に提供や指導をして、全てが先生であり同時に生徒と関係を作っていく。
そのサービスの交換代価を、ポイントシステムで管理してはどうだろうか。
“構想に対する懸念”
この構想の「お題目」は素晴らしいものですが、実行に当たっての具体的な内容がハッキリしない。
それにこの構想を実現するには、末端の県民の情報リテラシーが徹底的に不足している。
大きな構想は示すことは確かに必要なことだが、同時に足元をしっかり固めることも大事である。
両方が巧くバランスしなければ実現は無理だろう。
しかし、現在の佐賀県の状況は必ずしも好ましく無い。
県のトップは構想の実現に向けて意欲を見せてはいるが、行政の幹部がそれに付いて来ていない。役所の悪い癖で変化嫌うのだ。
でも誰が見ても現況で佐賀県が長期に渡って活性化する兆しは見えない。宮崎県知事ではないが、「どがんかせんといかん」状況だ。
これではトップには耳に気持ち良い事がばかりが伝わり、実際の現場は全然動いていない状況になるだろう。
歴史上どんなに優れた指導者でも、組織の情報の流れが滞り崩壊した例は枚挙にいとまがない。
情報化事業が、情報が原因で失敗していたのでは目も当てられない。
行政だけではない、小・中学校のICT分野の指導力不足ははっきりしている。
しかし、教師にそれを求めるのは無理なのも現状だ。
学校はもっと柔軟に外部の力を受け入れるべきだと思う。
社会教育を担う大学にも問題はある。お余りにも指導方法が一般人には馴染まないのだ。
もっと現場の目線での指導方法を研究してほしい。
民間企業にも問題がある。
特にこの事業の先頭に立つべきIT関連企業が、短期的な利益だけに目がいっている気がする。
そのために、事業そのものに反対に企業すら見受けられる。
もっと中・長期的視野での視点で事業に取り組んでほしい。
それが結果的には自社の利益につながるのだから。またそうしなければ生き残っていけない。
Posted by 昏君 at 00:37│Comments(0)
│地域活性化